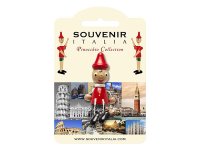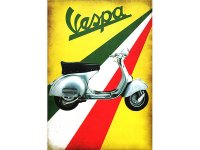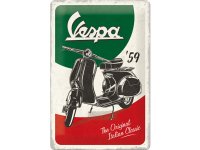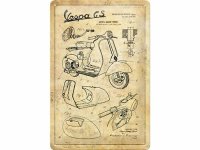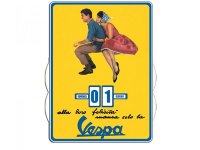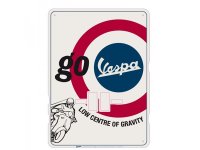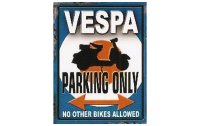ショッピングカート
カートは空です。
書籍
-
イタリア語版 日本の漫画
- 青山剛昌
- 暁月あきら
- 顎木あくみ
- 新川直司
- 浅野いにお
- 荒川弘
- 荒木飛呂彦
- 石田スイ
- 石ノ森章太郎
- 池田理代子
- 諫山創
- 井上雄彦
- 岩明均
- 浦沢直樹
- 大友克洋
- 奥浩哉
- 尾田栄一郎
- 小畑健 大場つぐみ
- 甲斐谷忍
- カネコアツシ
- 桂正和
- 岸本斉史
- 吾峠呼世晴
- 小山宙哉
- 今敏
- 新海誠
- 鈴木ジュリエッタ
- 惣領冬実
- 空知英秋
- 高橋留美子
- 武井宏之
- 谷口ジロー
- 手塚治虫
- 鳥山明
- 永井豪
- 中村光
- 弐瓶勉
- 八田鮎子
- はっとりみつる
- 花沢健吾
- 原泰久
- ハロルド作石
- 姫川明
- 平本アキラ
- 堀越耕平
- 藤子不二雄
- 藤巻忠俊
- 古舘春一
- 真島ヒロ
- 松本大洋
- 水木しげる
- 望月淳
- 森薫
- ヤマザキマリ
- 山本サトシ
- 山本英夫
- 幸村誠
- 技来静也
- ONE
- その他
-
イタリア語 書籍
- イタリアの新聞
- イタリア語 CILS
- イタリア語 CELI
- イタリア語 PLIDA
- イタリア語 教科書・参考書
- イタリア語 辞書・辞典
- イタリア語 オンラインビデオ, MP3, CD, DVD付き参考書
- イタリア語 オーディオブック
- イタリアなどのマップ
- イタリア発、世界中で人気の児童書 ジェロニモ・スティルトン
- イタリアの作家ウンベルト・エーコ
- イタリアの童話作家ジャンニ・ロダーリ
- イタリアを代表するコメディ ファントッツィ
- モンタルバーノ警部シリーズ - アンドレア・カミッレーリ
- イタリアを代表する漫画出版社 セルジョ ボネッリ エディトーレ
- イタリアのデザイナー・美術家ブルーノ・ムナーリ
- 日本の文庫 イタリア語版
- イタリア語で読む本
- イタリア旅行に
- カリメロの絵本
- ピンパの絵本
- 絵本・児童書
- スヌーピー
- 音楽
- Il cucchiaio d'argento - イタリアを代表する料理の本
- Slow Food - 料理の本
- Barilla - 料理の本
- イタリア料理 - 料理の本
- 聖書
- DVD・ブルーレイ
- 書籍 - アウトレット
- 他言語 書籍
知っておきたいイタリア
- Agip アジップ
- Alberto Sordi アルベルト・ソルディ
- Alessi アレッシ
- Alfa Romeo アルファロメオ
- Ape アーペ
- Barilla バリッラ
- Bauer バウエール - スープストックの老舗
- Bialetti ビアレッティのキッチンツール
- Bruno Munari ブルーノ・ムナーリ - イタリアを代表するデザイナー
- Caffarel カファレル
- Calimero カリメロ
- Carosello カロゼッロ
- CAMPARI カンパリ
- Cucchiaio d'argento イル・クッキアイオ・ダルジェント
- Colatura, Garum - イタリアの魚醤
- Colomba pasquale コロンバ・パスクアーレ
- Compasso d’oro コンパッソ・ドーロ
- D.O.S.トリュフ・スペチャリタ - トリュフ
- Fantozzi ファントッツィ - イタリアを代表するコメディ
- FERRARI フェッラーリ
- FIAT フィアット
- Filigrana sarda サルデーニャの伝統ジュエリー
- Geronimo Stilton ジェロニモ・スティルトン - イタリア発、世界中で人気の児童書
- Gianni Rodari ジャンニ・ロダーリ - イタリアの童話作家
- GOLIA ゴリア
- Guzzini グッツィーニ
- Ichnusa イクヌーザ
- ISO Rivolta イーゾ・リヴォルタ
- Italeri イタレーリ
- La Linea ラ・リネア
- Lambretta ランブレッタ
- La Secchia バルサミコ酢醸造所 - バルサミコ酢
- LAVAZZA - 1895年創業 イタリアの焙煎コーヒー製造会社
- Leonardo da Vinci レオナルド・ダ・ヴィンチ
- Manaresi マナレージ - 1898年 イタリアで最初のバール開業
- Marco Polo マルコ・ポーロ
- Martini マルティーニ
- MARVIS マルヴィス
- MENABREA メナブレア
- Montalbano モンタルバーノ警部シリーズ
- Mortaio モルタイオ - 大理石製乳鉢
- MOTTA モッタ
- Nutella ヌテッラ
- Olivetti オリヴェッティ
- OMADA オマダ
- Pandoro パンドーロ
- Panetone パネットーネ
- Parrozzo パッロッツォ - ペスカーラ発祥のスイーツ
- PETER'S TeaHouse - 高品質なハーブティー
- Pinocchio ピノッキオ
- Pimpa ピンパ - イタリアの絵本、アニメ
- RICHARD GINORI リチャードジノリ / GINORI1735 ジノリ1735
- Rose&Tulipani ローズ エ トゥリパー二
- San Benedetto サン・ベネデット
- Sambonet - 老舗テーブルウェアメーカー
- San Pellegrino サン・ペッレグリーノ
- Segafredo Zanetti セガフレード・ザネッティ
- Sergio Bonelli Editore セルジョ ボネッリ エディトーレ - イタリアを代表する漫画出版社
- Slow Food スローフード
- THUN トゥーン
- Umberto Eco ウンベルト・エーコ - イタリアの作家
- VESPA ヴェスパ
- お取り寄せ
QRコード


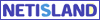

自動相互リンクサイト
外来語を一瞬で「使える」イタリア語に!

オーナー
 名前: YOKO |
神戸出身
イタリア、ミラノ郊外の街VARESE県在住
友達と会い、ミラノを歩き回る事が楽しみ
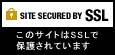
|
ホーム |
VESPA ヴェスパ
商品一覧
VESPA ヴェスパ
商品並び替え:
登録アイテム数: 15件
説明付き一覧 写真のみ一覧
説明付き一覧 写真のみ一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


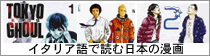

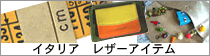
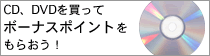
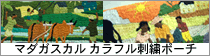
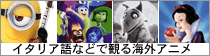

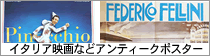


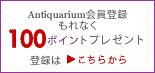

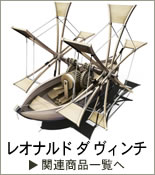
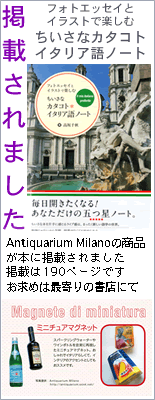
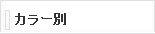



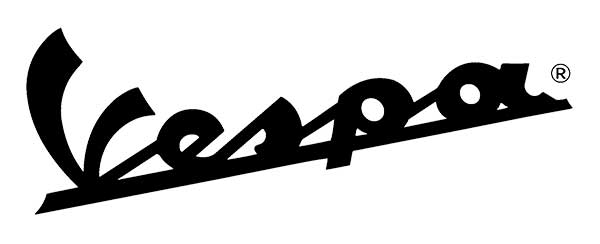
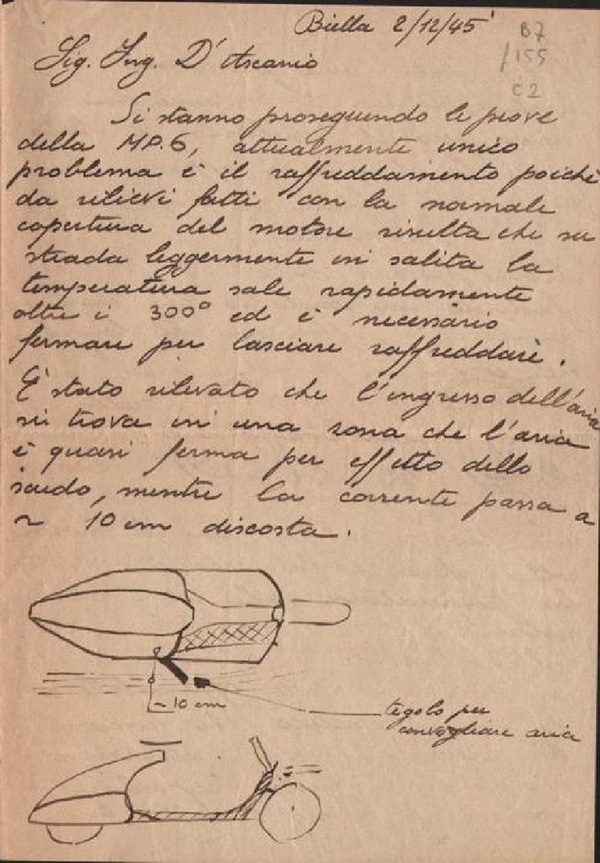
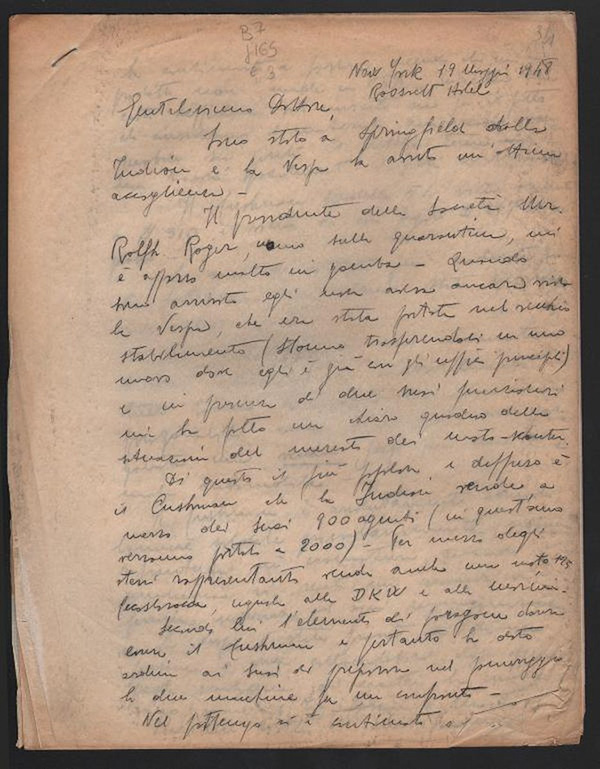
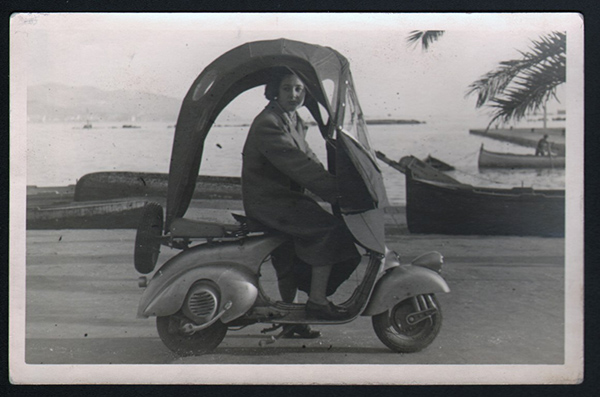
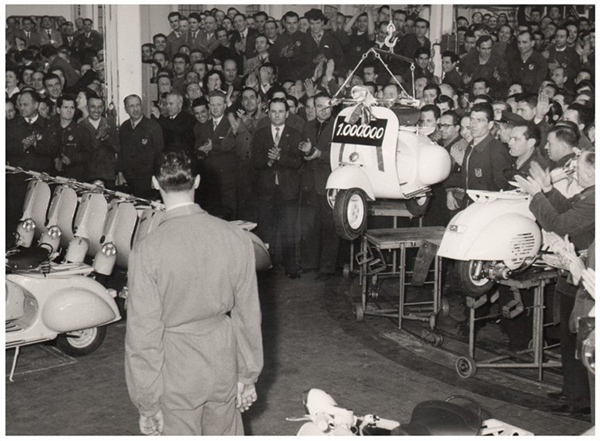
 >
>