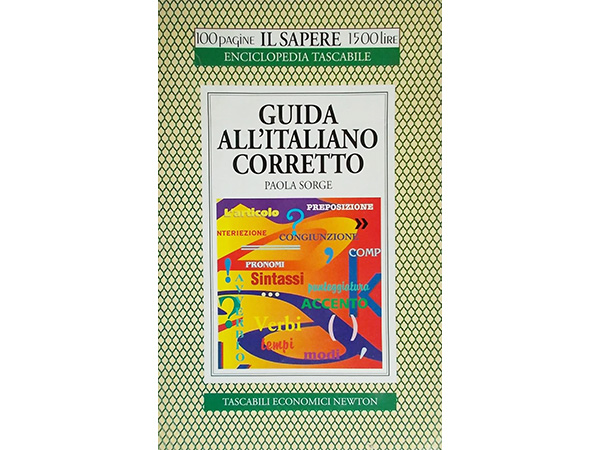Antiquarium Milano このページは、「正しいイタリア語のミニガイド Guida all'italiano corretto」(>商品ページへ)を当店Antiquarium Milanoが日本語に訳したものです。
正しいイタリア語へのミニガイド 自分の母語であるイタリア語なのに、ある単語の正しい書き方や発音に迷ってしまう。過去分詞の形に自信が持てない。名詞の複数形を作るときに「i」を入れるべきかどうか、動詞の活用で戸惑ってしまう。――そんなとき、人はふと「なんだか恥ずかしい」と感じるものです。自分が悪いことをしたような、どこか「人と違う」ような気持ちになってしまうのです。そして、そんな迷いを自分にすら認める勇気が出ず、ましてや文法書を開いて調べるなんてとてもできない。かえって挫折感が強まるように思えるからです。 そもそも多くの大人は、学校時代の文法の教科書なんてとっくに捨ててしまって、二度と買い直すこともありません。「イタリア語の規則は一度覚えれば一生忘れないものだ」と思い込んでいて、うっかり忘れたり間違えたりするはずがないと信じているのです。 けれど実際には、誰でも、特に文章を書く習慣や職業を持つ人ほど、数えきれないほどの疑問に出くわします。だからこそ、大切なのは「勇気」を出して古い規則を復習しなおすことです。それが私たちの言葉の土台だからです。 この小さな『正しいイタリア語のミニガイド - Antiquarium Milano』は、完全な文法書を目指したものではありません。すべての品詞や用法について触れていますが、誰でも知っているような基本の規則や説明はあえて省き、その代わりに「迷いやすいポイント」「間違えやすい箇所」に重点を置きました。名詞や形容詞の複数形の作り方、語と語の一致、句読点の使い方など――話したり書いたりする人が戸惑う部分を中心にまとめています。 【目次】アクセント 【アクセント】すべての単語にはアクセントがあります。もしくは、隣の単語のアクセントに依存して発音されます。例えば、一部の一音節語(特に冠詞など)は、自分では強く読まれず、次に続く語のアクセントに「寄りかかる」形になります:
また逆に、直前の語のアクセントに寄りかかることもあります:
前者のように後ろに寄りかかる一音節語を 前接詞(proclitici プロクリティチ) と呼び、後者のように前に寄りかかるものを 後接詞(enclitici エンクリティチ) と言います。 単語を発音するとき、声が特に強く置かれる部分の音節を 強勢音節(sillaba tonica シッラバ・トニカ) と呼びます(ギリシャ語の tònos = 力 に由来)。そのほかの音節は 弱勢音節(àtone アートネ) と呼ばれます。 アクセントの位置によって、イタリア語の単語は次のように分類されます:
書き言葉におけるアクセント記号イタリア語では、アクセント記号は通常書きません。
また、アクセントの位置によって意味が変わる語 もあります。この場合、混乱を避けるためにアクセントを記す必要があります。
アクセントの種類イタリア語のアクセントには アクート(´) と グラーヴェ(`) の2種類があります。
しかし実際には、特に語尾の -e の場合、正しく区別せずに適当に記号を付けてしまうことが多いのです。 混乱を避けるために、特に「e」で終わる単語 については、どの語がアクート(閉じた e)になるかを覚えておくとよいでしょう。 「é(閉じた e)」になる単語の例
一方で、語尾に「è(開いた e)」が付く名詞(例:caffè(コーヒー), tè(お茶))は、普通はグラーヴェ(è)が使われます。 アクセントで意味が変わる単語アクセントがアクート(é)かグラーヴェ(è)かによって、意味が変わる語もあります。
⚠️ 発音の違いが意味の違いにつながるため、注意が必要です。 よくある発音の迷い(I DUBBI)
このように、誤って広まっている発音がいくつかあります。特によくある例を挙げます:
以下は、実際には誤って使われることが多いけれど、正しくはこう読むべき という単語のリストです。
【冠詞】「冠詞」という言葉はラテン語 articulus(小さな関節・つなぐ部分)から来ており、名詞に密接に結びついてその性(男性・女性)を示します。冠詞には 定冠詞 と 不定冠詞 があります。 定冠詞(Articolo determinativo)
この定冠詞はラテン語 ille(あの、その)から発達しました。古典ラテン語の一部(例:プラウトゥス、キケロ)では ille が冠詞のように使われることがあり、その用法が徐々に広まって、イタリア語における定冠詞が成立したのです。 基本ルール
例:
論争点:ps, pn の場合
疑問(I DUBBI) 女性定冠詞
冠詞をつけない場合
疑問(I DUBBI)
疑問(I DUBBI)
不定冠詞(Articolo indeterminativo)由来はラテン語 unus(数字の「1」)。
部分冠詞(articolo partitivo)不特定の量を表すとき、前置詞 di + 定冠詞 を使います。 例:
これは「全体の一部」を表す冠詞で、部分冠詞 と呼ばれます。 前置詞と冠詞の結合(Preposizioni articolate)冠詞は前置詞と結合して「縮約形」になります。
例:dai libri(本から), dagli scolari(生徒たちから), agli gnomi(小人たちへ)。 スタイル上の注意(QUESTIONI DI STILE)
疑問(I DUBBI)手紙の日付に出てくる「li」とは何か?
特別な用法芸術作品を指すときには冠詞を使う:
【名詞】名詞(sostantivo)は 物・人・動物・行為・考え を表します。種類はいくつかあります:
こうした分類は自然に身についているので普段迷うことはありません。ただし「concreto と astratto の境界」などは哲学的な疑問もあります(例:Dio, anima)。 実際に迷いやすいのは 変化(declinazioni) です。
こうした疑問に答えるため、名詞の「変化(declinazioni)」を整理します。 Le declinazioni(変化形)名詞は 性(genere)と数(numero) によって形が変わります。 1. Prima declinazione
例外として:
疑問:asma は男性か女性か? 語尾 -cia / -gia の複数形
2. Seconda declinazione
男性単数 → 女性複数に変わる語
不規則な複数
-co / -go の複数
しかし例外多数:
二重形あり(両方正しい)
-logo / -fago (人に関する語) → 複数2形あり
-io の複数
3. Terza declinazione
両性あり
-ie 終わりは不変
例外(-e 脱落)
疑問:acme 4. Nomi indeclinabili(不変化名詞)複数も単数と同じ。
film の複数 → invariato(molti film が正しい) Il plurale dei nomi composti(複合名詞の複数形)規則的に変化するもの
形を変えるもの
不変化
capo を含む名詞
alto- / basso- 複合語二形あり:
トリッキーな場合(trattinoあり)
Nomi con due plurali(複数形が2つある名詞)例:
Maiuscole / minuscole で意味が変わる名詞
Dubbi frequenti(よくある疑問)
【形容詞】形容詞(aggettivo)は 名詞に付け加えられ、性(genere)と数(numero)に一致(concorda)する 語です。 1. Tipi di aggettivi(種類)a. Qualificativi(性質を表す形容詞)
b. Determinativi / Indicativi(限定・指示形容詞)
2. Dubbi frequenti(よくある疑問)
3. Declinazioni(変化)形容詞には 2つの変化(classi) がある。 Prima classe
Seconda classe
👉 複数の作り方は名詞と同じ規則が当てはまる。 特殊ルール:
複合形容詞 → 複数では 最後の要素だけ変化
4. Dubbi (altro)
5. Concordanza(一致の規則)
6. Comparativo e superlativoComparativo(比較級)
Forme speciali(ラテン由来の比較級)
👉 ✗ più migliore, più maggiore は誤り(重複)。 Superlativo(最上級)
特殊形(ラテン由来)
特殊な語
-fico 語尾 → superlativo in -ificentissimo
altro caso particolare
7. Dubbi finali
【代名詞】「pronome(代名詞)」はラテン語 pronomen(=「名詞の代わりに」)から来ており、名詞の代わりをする。代名詞は6種類ある:
人称代名詞(Pronomi personali)主格
👉 esso/essa/essi/esse は無生物・植物・動物に使う。 【疑問】 egli の代わりに lui を使えるか?一般に、特に口語では lui, lei, loro を主語として使うことが多い。 強形(forme toniche, 強勢形)と弱形(forme atone, 弱勢形)
特殊用法
【疑問】敬称の使い方
所有代名詞(Pronomi possessivi)
指示代名詞(Pronomi dimostrativi)
不定代名詞(Pronomi indefiniti)
関係代名詞(Pronomi relativi)
用法:
疑問代名詞(Pronomi interrogativi)
注意点:
相関代名詞(Pronomi correlativi)ペアで使う:
【動詞】ラテン語 verbum = 言葉 に由来し、動詞は「本当の言葉」「言葉そのもの」とされます。動作・状態・出来事を表し、それが 誰によって・いつ・どのように 行われるかを示します。 1. 動詞の種類
2. 他動詞と自動詞
3. 再帰動詞(riflessivi)
4. 活用(coniugazione)ラテン語 jugum(結びつき)に由来。語幹+語尾の組合せで 人称・数・時制・法 を表す。
※ 不規則変化・複数形の特殊例も多数。 5. 助動詞(ausiliari)
6. 動詞の種類
7. 時制(tempi)
8. 法(modi)7種類に分けられる:
9. 欠陥動詞(verbi difettivi)語形が揃っていない動詞:addirsi(si addice), aggradare(aggrada)など。 10. 過剰動詞(verbi sovrabbondanti)2つの活用を持つ:
11. 不規則動詞(verbi irregolari)例:andare, fare, dare, stare など。 【副詞】ラテン語 ad verbum = 動詞のそばに から派生。
副詞は形容詞と同じく 比較級・最上級 を持つ。 1. 副詞の種類(1) 仕方・様子の副詞(avverbi di modo o maniera)「どう?どのように?」に答える。
また come, così は疑問文・感嘆文でも副詞:
副詞句(locuzioni avverbiali):
(2) 場所の副詞(avverbi di luogo)「どこ?」に答える。
⚠️ 誤用注意
場所の副詞としての ci, vi, ne
(3) 時間の副詞(avverbi di tempo)「いつ?」に答える。
補足:
副詞句:una volta(一度), un giorno(ある日), di buon’ora(早朝に) (4) 量・程度の副詞(avverbi di quantità)「どのくらい?」に答える。
(5) 肯定・否定・疑問の副詞
2. 副詞の比較級・最上級
3. よくある疑問・誤用
【前置詞】ラテン語 prae-ponere = 「前に置く」に由来しており、実際に前置詞とは、名詞・形容詞・代名詞・動詞・副詞の前に置かれて、関係を示す語である。 前置詞は三種類に分けられる:固有前置詞(proprie)、転用前置詞(improprie)、前置詞句(locuzioni prepositive) である。 固有前置詞 とは、本来から前置詞である語である: 最初の五つは定冠詞と結合して、前置詞と冠詞の結合形(preposizioni articolate) を作る: collo, colla, cogli および pello, pegli, pelle という形は廃れてしまい、代わりに con lo, con la, con gli, per lo, per gli, per le と言うのが好まれる。 スタイル上の注意(QUESTIONI DI STILE)tra と fra は同じように使えるが、音の繰り返しは避けるのがよい:
イタリア語における前置詞の使用は簡単ではなく、しばしば混乱や誤用が見られる。 例:
転用前置詞(preposizioni improprie) は、副詞・名詞・形容詞・現在分詞などが前置詞の意味で用いられるものである。
スタイル上の注意(QUESTIONI DI STILE)官庁用語でよく使われる以下の表現は不自然である: 形容詞や名詞が前置詞として使われる場合: 現在分詞が前置詞として使われる場合: また過去分詞 eccetto(= eccettuato, 除外された)もある。 前置詞句(locuzioni prepositive) は、転用前置詞の後にもう一つの前置詞が続いたもの: また、前置詞句には前置詞 + 名詞(または副詞)の形もある: fuori は常に補強の前置詞 di または da を伴う: ただし、慣用句としては例外がある: スタイル上の注意(QUESTIONI DI STILE)
疑問(I DUBBI)
【接続詞】接続詞とは、二つまたはそれ以上の単語や文を「つなぐ」語である。 接続詞は、単純接続詞(semplici)、複合接続詞(composte)、接続詞句(locuzioni congiuntive) に分けられる。
接続詞は、二つの節を結びつけることで、それらの間に等位あるいは従属の関係を作り出す。したがって、接続詞には等位接続詞(coordinative)と従属接続詞(subordinative)とがある。 等位接続詞(Le congiunzioni coordinative)等位接続詞は、一つの文の中で同等の機能を持つ二つの節を結ぶ。
従属接続詞(Le congiunzioni subordinative)従属接続詞は、一つの節をもう一つの節に従属させる。
疑問(I DUBBI)
例:
【感嘆詞】感嘆詞(ラテン語 interjectio = 「挿入」)または「間投詞」とも言うのは、心の本能的な動きを表す言葉です。 固有の感嘆詞(=それ自体が感嘆詞であるもの)は:
もちろん、感嘆詞にどんな意味を持たせるかは、用いる声の調子によって決まります。 不完全(転用)の感嘆詞(=もともと別の品詞だったものが感嘆として使われるもの)は: 不完全感嘆詞の中には次のようなものもあります:
感嘆表現(句の形をとるもの) には、 【構文】文法(grammatica)が単語をそれぞれ独立して、他の単語と切り離して研究するのに対し、構文(syntassi:ギリシャ語 syntaksis = 配置、連結)は、単語同士を結びつける関係を研究するものです。 文(La proposizione)
述語(Il predicato)述語は、主語の活動・状態・性質を示します。述語には動詞述語(predicato verbale)と名詞述語(predicato nominale)があります。
目的語(Il complemento oggetto)目的語または直接目的語(complemento oggetto diretto)は、動作を受ける対象を示します。 不定詞(目的不定詞)が目的語の場合のみ、前置詞 di, a, da を伴います: 疑問(I DUBBI)文中で主語と目的語をどう区別するか?
文には、不可欠要素のほかに、修飾要素(属性、同格、間接目的語)が含まれることがあります。 属性(Attributo)と同格(Apposizione)文は、不可欠要素(主語・述語)に加えて、主語、名詞述語、目的語に関する形容詞や名詞を持つことがあります。
この場合、come regista と da amico は副詞的同格(apposizioni avverbiali)で、補語ではありません。 間接目的語(I complementi indiretti)間接目的語は動詞が表す動作の付加的要素です。間接的であるのは、前置詞に導かれ、時間、場所、原因、方法などを示すためです。 前置詞 di が導く主な間接目的語:
疑問(I DUBBI)文 mi portò dei cioccolatini や quelli sono dei ladri では、前置詞 di はどの補語を導くか?
前置詞 a が導く主な補語
前置詞 da が導く主な補語
前置詞 in が導く主な補語
前置詞 con が導く主な補語
前置詞 per が導く主な補語
疑問(I DUBBI)同じ前置詞が導く様々な補語はどう区別するか?
前置詞 su が導く主な補語
前置詞 tra / fra が導く主な補語
その他の補語
疑問(I DUBBI)評価補語(complemento di stima)と価格補語(complemento di prezzo)の違いは?
【文節】文(proposizioni)は互いに結びついて、より大きな構造、すなわち文節(periodo)を形成することがあります。 主文(La proposizione principale)文節には常に主文が存在します。これは他の文に文法的に依存しない文です。 主文には以下の種類があります:
従属文(Le proposizioni subordinate)従属文(subordinate / secondarie / dipendenti)は、単独では成立せず、主文に依存する文です。 従属文の種類:
挿入文(Le proposizioni incidentali)挿入文(parentetiche)は他の文に文法的関係を持たず、独立した観察や説明を加えるために用いられます。 等位接続(La coordinazione)文節内で、主文や従属文は等位接続によって結びつけることができます。 等位接続の方法:
【間接話法】直接話法(discorso diretto)から間接話法(discorso indiretto)に移行する際には、特に動詞の法や時制に関して一連の変化が生じます。 特に注意すべき点は以下の通りです:
各種文を導く主な接続詞
【句読点】句読点をうまく使うことは、一見簡単に思えるかもしれませんが、実際にはそう簡単ではありません。その役割は単に話の間を示すことだけではなく、表現、ニュアンス、イントネーションを伝えることにあります。 コンマの位置ひとつで、文全体の意味が変わることもあります。また、句点(ピリオド)、省略記号、感嘆符を多用しすぎると、文の優雅さが取り返しのつかないほど損なわれることがあります。 しかし、与えるべきルールは少なく、コンマ、セミコロン、コロンの選択は、書き手の感性や趣味によるところが大きいです。良い句読点の使い方は、読むことと書くことを習慣的に行うことで初めて身につきます。そのため、ここでは一般的な指針だけを示します。
【略語】タイトル、形容詞、丁寧表現や感謝の表現、さらには弔意の表現、案内や注意書きなどは、簡略化のため、あるいは便利さのために、1音節や、すでに一般的に使われる略号に縮められることが多いです。 略語の氾濫の中で迷わないように、特に公式文書や商業文書、文学、科学文書、脚注などでよく出会う、一般的な表現の一覧が役立ちます。 略語を作るには、正確なルールがあります:
よく使われる略語一覧(Le abbreviazioni più comuni)
【規則動詞の活用】第一活用:lodare(ほめる)直説法(Indicativo)
半過去(Imperfetto)
遠過去(Passato remoto)
単純未来(Futuro semplice)
現在完了(Passato prossimo)
大過去(Trapassato prossimo)
遠大過去(Trapassato remoto)
前未来(Futuro anteriore)
接続法(Congiuntivo)
過去形(Passato)
半過去(Imperfetto)
大過去(Trapassato)
条件法(Condizionale)
過去形(Passato)
命令法(Imperativo)
未来形(Futuro)
不定詞(Infinito)
分詞(Participio)
動名詞(Gerundio)
第二活用:credere(信じる)直説法(Indicativo)
半過去(Imperfetto)
遠過去(Passato remoto)
単純未来(Futuro semplice)
現在完了(Passato prossimo)
大過去(Trapassato prossimo)
遠大過去(Trapassato remoto)
前未来(Futuro anteriore)
接続法(Congiuntivo)
過去形(Passato)
半過去(Imperfetto)
大過去(Trapassato)
条件法(Condizionale)
過去形(Passato)
命令法(Imperativo)
未来形(Futuro)
不定詞(Infinito)
分詞(Participio)
動名詞(Gerundio)
第三活用: servire(仕える/役立つ)直説法(Indicativo)
半過去(Imperfetto)
遠過去(Passato remoto)
単純未来(Futuro semplice)
現在完了(Passato prossimo)
大過去(Trapassato prossimo)
遠大過去(Trapassato remoto)
前未来(Futuro anteriore)
接続法(Congiuntivo)
過去形(Passato)
半過去(Imperfetto)
大過去(Trapassato)
条件法(Condizionale)
過去形(Passato)
命令法(Imperativo)
未来形(Futuro)
不定詞(Infinito)
分詞(Participio)
動名詞(Gerundio)
受動態(Essere amato=愛される)直説法(Indicativo) 現在形(Presente)
半過去(Imperfetto)
遠過去(Passato remoto)
単純未来(Futuro semplice)
現在完了(Passato prossimo)
大過去(Trapassato prossimo)
遠大過去(Trapassato remoto, raro)
前未来(Futuro anteriore)
接続法(Congiuntivo) 現在形(Presente)
過去形(Passato)
半過去(Imperfetto)
大過去(Trapassato)
条件法(Condizionale) 現在形(Presente)
過去形(Passato)
命令法(Imperativo) 現在形(Presente)
未来形(Futuro)
不定詞(Infinito)
分詞(Participio)
動名詞(Gerundio)
Antiquarium Milano |